故人のアバターが会葬者に語りかけるサービスは、メディアでたびたび取り上げられる一方、死者への冒涜と受け止める声も少なくない。多くの人が感じる違和感は何に起因するのだろうか。
AIが故人のアバターを生成する
さいたま市に本社を置く冠婚葬祭企業が提供する、AIが故人のアバターを生成するサービスがちょっとした物議を醸している。葬儀会場で、自分の生涯や参列者への感謝を故人自身が語るビデオレターが上映されることは珍しくない。このサービスのポイントの一つは生前に作成する必要があるビデオレターを、遺族が提供した動画や写真に基づき、後追いで作成できる点にある。アバターが読み上げるメッセージは遺族が用意するが、それを考える過程が故人を振り返る機会になったと利用者には好評だ。サービスを提供する企業は、AIが生成した故人のアバターを今後、自社が運営するメタバース霊園サービスや納骨堂のサイネージと連携することで、いつでも故人と再会できるサービスを展開する予定だという。
だが、AIによりビデオレターの「フェイク」を作ることを死者への冒涜と感じる人も少なくないようだ。思い出されるのが、2019年のNHK紅白歌合戦にAIで復活した美空ひばりが出場した際の反応だ。美空ひばりの没後30年を記念し、最先端の音声合成システムを駆使してレコーディングされた新曲『あれから』は、その制作プロセスがNHKの番組で特集されるなど、当時大きな話題になった。最先端の映像生成テクノロジーを生かしたAIアバターによる紅白出場は一連のプロジェクトのゴールでもあったはずだが、その評価はまさに賛否両論だった。
当時のAI美空ひばり動画は今もネット上で確認できるが、それを見て技術の陳腐化の速さに驚く人も多いだろう。今日の観点では、映像はあまりに不自然で、最先端の合成音声技術を駆使して再現したという歌声も、不世出の歌手の生の声と比べるとチープという印象が拭えない。翌年が明けて間もなく、シンガーソングライターの山下達郎は自分のラジオ番組で「冒涜」という強い言葉を使って非難しているが、その言葉の背景に、当時の技術の限界もあったことは間違いないはずだ。
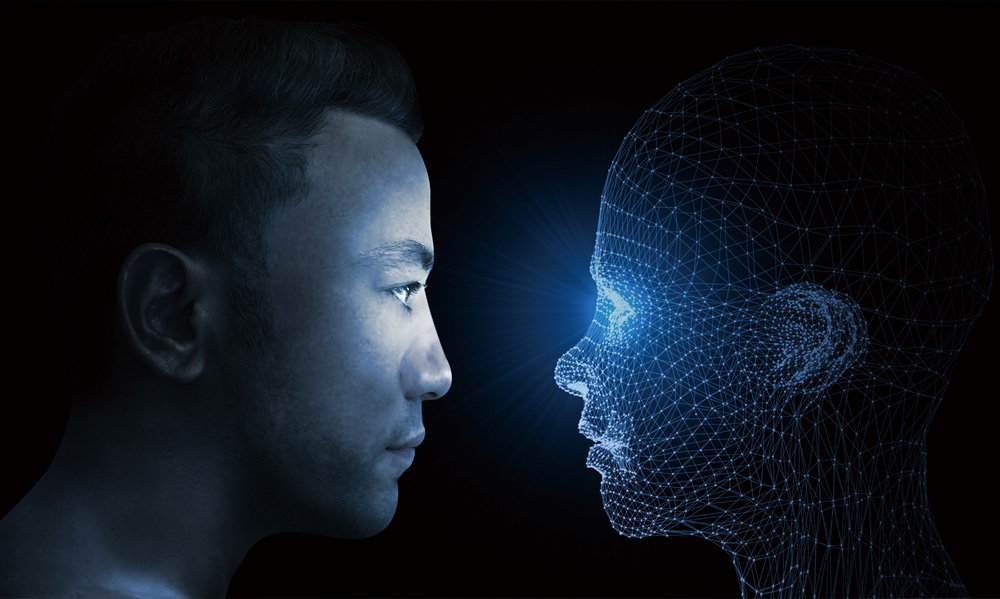
人格を再現するエージェントの役割
「亡くなった歌手のアバターが新曲を歌うという試み自体は興味深い。だが何らかのメッセージを死者に語らせるのは違うのではないか」。AI美空ひばりへの否定的な意見を一口に言えばこうなる。既に紹介したとおり、メッセージ自体は他愛もないものだ。だが死者のアバターに本人のものではないメッセージを語らせることへの違和感は、AI故人サービスへの反応とも共通する。
ではそれが、遺族や第三者が考えた言葉ではなく、AIが学習した故人の人格に基づくサービスだったとしたらどうだろうか。実は故人のアーカイブをAIが学習し、チャットボットとして提供するサービスはアメリカや中国で既に普及が進んでいる。AIの進化もあり、データが用意できるのであれば、人格の再現はそれほど難しいことではない。右翼的な思想を持つユーザーに支持されるアメリカのSNSは、著作を通してヒトラーの人格を再現したチャットボットを開設し物議を醸したが、その程度のことであれば簡単にできてしまうのが実情だ。膨大な著作を残したヒトラーのケースと違い、一般人は参照すべきデータ量の少なさが課題の一つだが、SNSの普及に伴うデジタルデータの蓄積はそれを乗り越える上で大きな役割を果たすことになるだろう。では、故人のアーカイブに基づき再現された人格の言葉を紹介することは死者の冒涜にあたるのだろうか。その答えは簡単ではない。
最後にAIによる人格再現のもう一つの重要な意義について触れておきたい。昨年、スタンフォード大学とGoogleの研究チームは、AIによる2時間程度のインタビューをLLMに取り込むことで、有意な特徴を備えるエージェント構築に成功したことを発表した。これまで経済学など社会科学領域では、理論の正しさを証明するには大規模な社会実験を行うほかなかった。経済政策や少子化対策など、我々が直面する課題への対応の難しさもそこにある。実在する人格を再現するエージェントは、社会が直面する課題の迅速な解決に大きな役割を果たすことが期待されている