SIMフリースマホビジネス特集
第10回 ~2017年、春・夏のデバイス 編~

大手キャリアの回線を利用したMVNO(仮想移動体通信業者:Mobile Virtual Network Operator)と通信回線を自由に選べるSIMフリーデバイス。ようやくエンドユーザー様に理解されてきたキーワードは、パートナー様のビジネスの一翼を担う市場として成長しつつある。そこで、今回は2017年の春から夏に向けておすすめのSIMフリーデバイスやWi-Fiモデルから、日本市場での実績が十分のHUAWEIやASUSの製品を紹介したい。
多くのMVNO事業者が選ぶ、HUAWEIとASUSの製品
日本でもようやく理解が進んできたMVNO。スマートフォンの普及に伴い、通信コストを抑える手段として注目を集めている。回線契約をデータ通信に絞り、通話はIP電話アプリで補うといった使い方をすれば、柔軟な契約ができ、コストメリットの高い運用方法が可能だ。近年は法人向けのサービスを提供するMVNO事業者も増えてきており、データ通信専用SIMを利用するには、月額数千円のデータ通信量で10GB以上のデータを利用できるものも珍しくはない。
回線契約と同時に端末を販売するMVNO事業者もあるが、その多くは中国のHUAWEIや、台湾のASUSの製品をラインアップに入れている。両者ともコストパフォーマンスに優れる製品を多く世に出しており、なおかつ製品性能の信頼度が高いことが選択されている理由ではないだろうか。そこで今回は、2017年の春から夏に向けておすすめのSIMフリーデバイスをHUAWEIやASUSの製品から紹介したい。
トータルバランスに優れるHUAWEI製スマートフォン

HUAWEI製スマートフォンの主要なラインアップは、「HUAWEI Mate 9」「HUAWEI P9/lite」「HUAWEI nova/lite」の3種類。いずれも最新のAndroid 7.0を搭載し、オクタコアCPUの採用で快適なオペレーションを実現している。特にフラッグシップモデルの「HUAWEI Mate 9」はメインメモリー4GBや約5.9インチの大型ディスプレイを搭載。メインカメラはダブルレンズと、精細な写真撮影を実現している。3機種とも大容量バッテリーを搭載し、長時間の稼動が可能。高感度の指紋認証センサーも搭載しており、スムーズかつセキュアな環境を実現している。
一芸に秀でるASUS製スマートフォン。AR・VR対応の意欲的なモデルも

ASUSの主力スマートフォンは「ZenFone 3」シリーズだ。フラッグシップモデルの「ZenFone Deluxe」からエントリー機まで、豊富なラインアップを取りそろえている。主要モデルの「ZenFone 3」は2GHzの省電力オクタコアCPUや4GBのメインメモリーを搭載したスキのない性能。カメラも1,600万画素センサーや、約0.03秒の高速AFも備えており、高精細の写真を軽快に撮影できる。
また、一芸に秀でたラインアップがあるのも、ASUS製品の特徴。「ZenFone 3 Max」は、1,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大約38時間の待ち受けや、最大19時間のブラウジング(Wi-Fi通信下)を実現している。
さらにARおよびVR機能を標準で搭載した意欲的なモデルも。この夏に発売が発表された「ZenFone AR」は、ハイエンド向けのCPUと8GBの大容量メインメモリーを採用し、次世代AR技術「Tango」と、スマホVR技術「Daydream」に最適化された圧倒的なパフォーマンスを実現している。多種多様な端末を利用形態に合わせて選べるのがASUS製品の強みといえる。
iPadに引けを取らないHUAWEI製タブレット
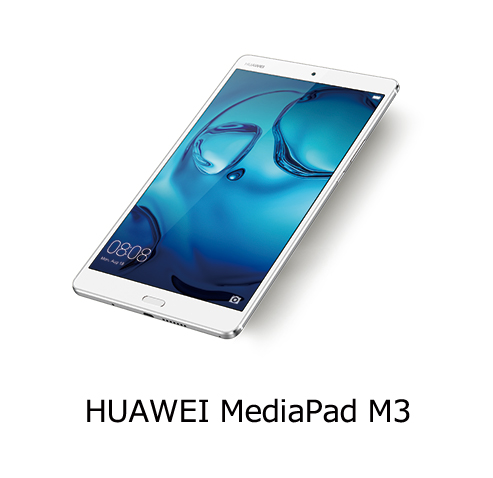
iPadの後塵を拝している感のあるAndroidタブレットだが、近年ではApple製品に迫る製品も出始めている。作画などクリエイティブな領域ではまだアプリの面でiPadに軍配が上がるが、ビジネス用途に限って言えば、HUAWEIの「MediaPad」シリーズは必要十分な性能を満たしている。何よりも容易にSIMフリー品が手に入るため、MVNOで利用しやすい。
フラッグシップモデルの「M3」は2,560×1,600ドット(359ppi)の高精細な8.4型ディスプレイを搭載。独自の画像最適化技術の採用により、鮮明な画像表示はもとより、ブルーライトや輝度の低減により、目への負担を軽減する機能も用意している。高速CPUや大容量5,100mAhバッテリーの採用により、快適な動作環境を長時間保つことが可能だ。
両方ともスタイリッシュな薄型のWindows 10搭載ノートPCも充実
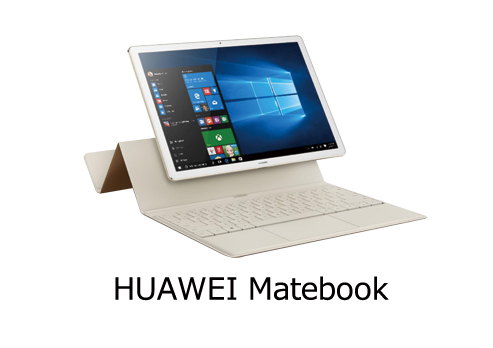
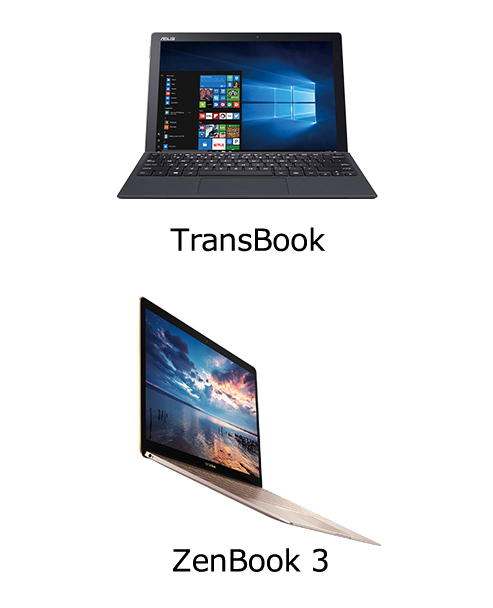
両社ともに、Windows 10搭載の薄型PCも手がけている。HUAWEIのMatebookは2in1モデルで、単体で厚み約6.9mm、重さも約640gと非常にコンパクト。専用キーボードも約500gと、軽快に取り回せる。それでいてCPUには第6世代のIntel Core mプロセッサー、メインメモリーは最大8GB、ストレージは最大512GBのM.2SSDを採用と高スペックを誇る。ディスプレイは2,160×1,440の12インチIPSタッチパネルを採用。2,048段階の筆圧を検知する高感度センサー搭載電子ペン「MatePen」が付属し、精密な手書き操作も可能。ペンはレーザーポインターも搭載するなど、プレゼンテーション操作まで行える。
ASUSの「Zenbook 3 UX390UA」は、11.9mm厚の薄型ノートPC。CPUには省電力タイプのCore i7を採用、メインメモリーは8〜16GB、ストレージは256〜512GBのSSDと、ノートPCとしては破格の性能だ。最上位モデルはSSDがPCI Express 3.0 x4接続で、高速なアクセスを実現している。ASUSは2in1モデルの「TransBook T304UA」も手がけており、やはりスマートフォン同様、選択の幅が広い。
HUAWEIとASUSの製品は、どれもビジネスに要求されるスペックを過分に満たしてくれる。業務の形態に合わせてスマホやタブレット、PCを組み合わせ、MVNOの運用も含めエンドユーザー様に提案していただきたい。
