
アイ・オー・データ機器:HDL-Z4WLI2シリーズ
Intel Core i3と大容量8GBのメモリーを搭載しているので、エンドユーザー様はサーバー使用時と遜色のない使い勝手を実感できるだろう。サーバーからの移行時、故障の際の復旧時にも無償専用ソフト「Sync with Business Edition」でスムーズに作業が行え、管理者の負担を減らしてくれる。
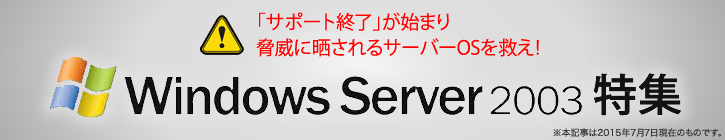
いよいよ、Windows Server 2003のサポートが終了する。一般のメディアでは、Windows XPのサポート終了時ほどは取り上げられていない。そのせいか、サポートの終了そのものを知らない、あるいはその影響をきちんと理解していない、というエンドユーザー様は少なくない。しかし、データやアプリケーションを司ることが多いサーバー機器では、僅かなほころびだけで大規模な事故を招く恐れがある。情報とは企業の重要な資産であるだけでなく、外部へ漏洩した場合に大きなリスクを伴う、言うなれば「諸刃の剣」だ。エンドユーザー様の環境をしっかりと把握して、適切な提案をしていただきたい。
Windows Server 2003のサポート終了について、当事者であると意識している中小企業者は少ないのが実態だ。その理由はいくつか考えられるが、大きく2つに分けることができるだろう。
1つめは、そもそもWindows Server 2003のサポート終了自体を知らない、さらには、Windows Server 2003を使っていることすら把握していない、というケースだ。このようなエンドユーザー様には、イチから説明が必要になる。
2つめは、セキュリティソフトがあるから問題ないと考えているケースだ。サポート終了が脆弱性と関係することは理解しているが、脆弱性についての理解が不十分なのである。仮想化しているから問題ないというエンドユーザー様も、このカテゴリーに分類される。多少は知っている、しかし、知識が不十分、あるいは間違った理解をされている場合には、誤解を解くところから説明を始める必要がある。
いずれの場合にも、まずは正しい知識をエンドユーザー様に理解してもらう必要がある。日常的に認識することの少ないサーバーOSの役割や、セキュリティの基本的な考え方について、分かりやすい説明資料を用意するなどの事前準備も重要だ。
また、Windows Server 2003を使用しているかどうかを把握していないというエンドユーザー様については、サーバー環境の調査から始める必要がある。調査サービスを提供しているベンダーもあるので、活用をおすすめいただきたい。
日本年金機構や東京商工会議所の情報漏洩事件が記憶に新しい。これらの事件とOSのサポート終了を結びつけるのはいささか短絡的に過ぎるが、リスクをイメージしてもらうには有効だろう。サポートが終了した、すなわちセキュリティパッチが提供されないWindows Server 2003を使い続けるリスクを理解してもらうことが、最初のステップになる。
次のステップは、お客さまのどのサーバーでWindows Server 2003が使われているのかを把握することだ。サーバー機器はその用途によって、異なる対応を提案する必要がある。アプリケーション、メール、ウェブなどさまざまな役割があるが、中小企業でもっとも多いのはファイルサーバーでの運用だ。
IDC JAPANが2014年10月に実施したユーザー調査では、当時残存しているWindows Server 2003採用サーバーの67.7%がファイルサーバーとしての稼働だと回答されている。さらに、サポート終了後も18.6%はそのままファイルサーバーを使い続けるとしており、今後もリプレースの需要は残されているといえる。
ハードウェア、OS、ソフトウェアを含めて、エンドユーザー様がどのようなIT環境であるのかを把握するためには、今回のWindows Server 2003のサポート終了は絶好の機会といってもよい。
セキュリティ対策は、自動車のシートベルトに似ている。サポート終了はシートベルトが付いていない車を運転するようなものだ。事故は予期せぬタイミングで突然起こる。中小企業がIT部門に割ける予算は限られているが、だからこそ最低限の対策が必要であることを訴えていただきたい。
では、具体的にはどのような提案が有効だろうか。サーバーリプレースの選択肢はサーバー機器のリプレース、クラウドへの移行、オンプレミスと組み合わせたハイブリットクラウドなど多様に存在する。もちろんエンドユーザー様の環境・条件に合わせて、全選択肢を提示できる準備は必要不可欠だ。
このなかで、本サイトでは周辺機器の観点から、前述した『ファイルサーバー』のリプレース、そしてバックアップ機器の提案を強くおすすめしたい。メリットとしては低コスト、管理負担の軽減、規模に応じた必要十分な配置が可能な点だ。エンドユーザー様の環境に最適で最小限の構成を提案していただきたい。
BP事業部ではファイルサーバーのリプレース提案として、以下4つのNAS製品をおすすめしたい。各メーカーの特色をまとめているので、参考にしていただきたい。

Intel Core i3と大容量8GBのメモリーを搭載しているので、エンドユーザー様はサーバー使用時と遜色のない使い勝手を実感できるだろう。サーバーからの移行時、故障の際の復旧時にも無償専用ソフト「Sync with Business Edition」でスムーズに作業が行え、管理者の負担を減らしてくれる。

独自の技術「Beyond RAID」によって、異なるディスク容量・メーカー・型番のHDDやSSDでもRAID構築が可能。足りない分のストレージを購入するだけでRAID構築できるので、コストを抑えることができる。故障した際にも最大2台までのディスク同時障害に対応し、より万が一の備えがあるのは心強い。

本体及びHDDともに3年の保証期間内であれば無償修理に対応しているので、長期間安心して運用することができる。また、1台でNASとiSCSIストレージを同時に使用できるので、ファイルサーバーとして使用しながら、サーバー用ストレージとしても活用するといった多目的な運用ができるのも魅力だ。

独自の管理ソフトウェア「ロジテックツール」を標準搭載し、RAIDエラーや不正電源切断などのイベント情報を管理者にメール通知したり、RAIDのリビルドや構成変更といったメンテナンスを補助してくれる。信頼のNAS向けHDD「WD RED」を採用した高い耐久性も、アピールポイントとなるだろう。
また、リプレースのみで終わらせてしまっては、商機として物足りない。この機会に、BCPやDR対策の着手や強化をあわせて提案してはいかがだろうか。バックアップ機器については、以下の製品をおすすめしたい。

RDXドッキングステーションとRDXカートリッジ、小冊子「サーバーバックアップ入門」がセットになっており、初心者でも簡単にバックアップを始めることができる。セキュリティを強化したい場合には別売のRDXカートリッジセキュアも使用でき、最初の一手として導入しやすいスターターキットだ。
直前に迫った課題のみを解決するだけでは、ただのイタチごっこになってしまう。IT環境の調査から浮き彫りになった新たな課題を洗い出し、プラスアルファの提案に結び付けることで、エンドユーザー様の満足度さらにを高めていただきたい。
日本マイクロソフトはサポート終了時点で約5万台にまで対象サーバーを減らすことを目的に掲げているが、言い換えれば、それでもまだ5万台もWindows Server 2003サーバーが残っているということになる。新たな脆弱性が発見されても、修正プログラムが提供されなくなり、エンドユーザー様の環境は常にウイルスなどのマルウェアの脅威に晒されることになるのだ。
サポート終了に関わる商機について提案してきたが、もっとも重要なのは、サポート終了によってエンドユーザー様が不利益を被らないことである。取りこぼすことなくWindows Server 2003サーバーを発掘し、エンドユーザー様、販売パートナー様双方が納得できる提案を実現していただきたい。