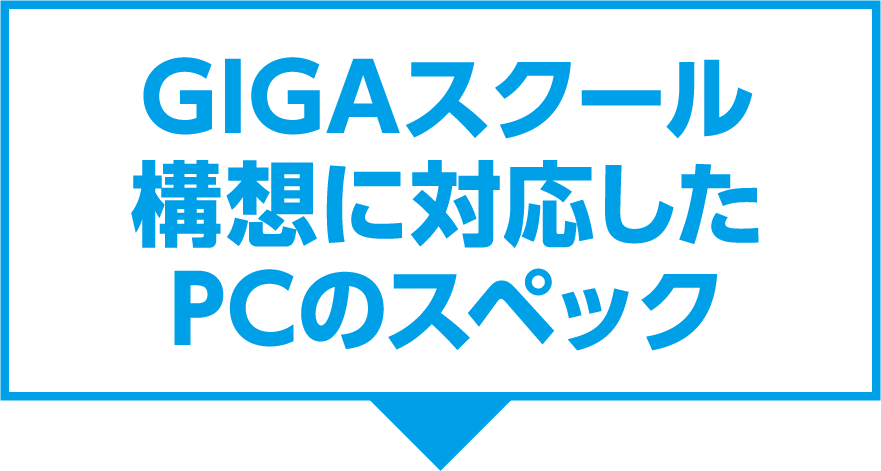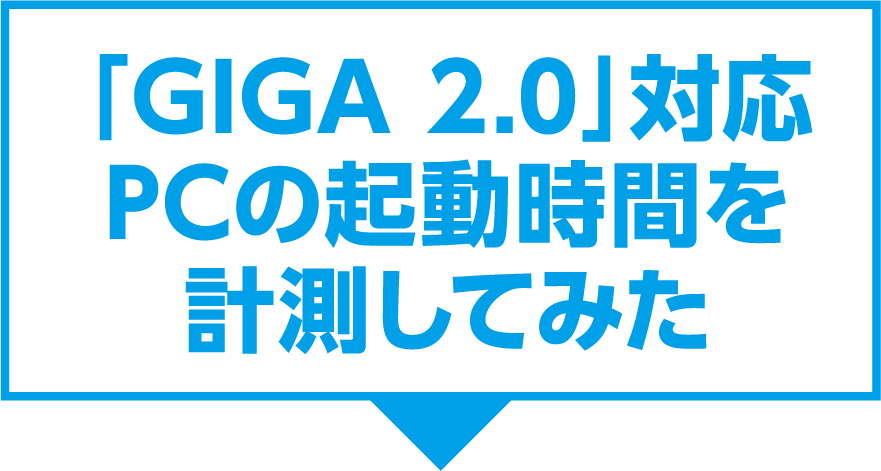GIGAスクール構想に
対応したPCのスペック

2019年12月、文部科学省は、児童・生徒に1人1台のPCの実現を目指す「GIGAスクール構想」を発表し、全国の小中学校のICT環境の整備支援を急ぐことになった。
当時のWindows端末の具体的な仕様は、OSがWindows 10 Pro相当、CPUが2016年8月以降に製品化されたIntel Celeron同等以上、メモリが4GB以上、ストレージが64GB以上とされている。
日頃からPCを活用しているビジネスパーソンの立場からの感想では、決してスペックは高くない。むしろ使えるかどうか不安になるほどだ。こうした低スペックのPCが標準仕様として策定された背景にあるのが、端末整備の補助金が1台4万5,000円までとされていたことにある。
ところが、ある調査機関で発表された結果によると、各自治体の教育委員会へのヒヤリングでは、回答者の92%が対応PCのスペックは、「十分に備えている」「備えている」との返答がえられたようだ。これはどういうことだろう。
実は、クライアントOSとしてのWindowsのシステム要件はそれほど厳しくない。
Windows 10 のシステム要件
- プロセッサ: 1 GHz 以上のプロセッサまたは SoC
- RAM: 1 GB(32 ビット)または 2 GB(64 ビット)
-
ハードディスクの空き容量:
16 GB(32 ビット OS)または
20 GB(64 ビット OS) - グラフィックス カード: DirectX 9 以上および WDDM 1.0 ドライバー
前述した各教育委員会のヒヤリングにおいて、PCの具体的な用途を複数回答で聞いたところ、最も多いのは「学習支援ソフトやアプリの利用」と「調べ学習」(69%)だった。3位は「考えをまとめて発表」(61%)、4位は「デジタル教科書・ドリル」(51%)、5位は「カメラ機能で動画や写真を撮る」(50%)と続いた。他には「生徒と児童・生徒のやりとり」(44%)、「児童生徒同士のやりとり」(32%)もあった。
結果として、用途を絞った使い方であれば、補助金の予算内のPCで授業は可能という意見が見受けられたという結果だった。
次世代のGIGAスクール構想「GIGA2.0」
GIGAスクール構想が前倒しで整備されたことで、導入から4年以上経った端末が出てきており、端末更新が必要となってきた。この端末更新計画は通称「GIGA2.0」や「NEXT GIGA」と呼ばれており、2024年1月に文部科学省の基本方針が公表された。
GIGAスクール構想と異なる主な点は「国の予算で都道府県に基金を造成し、そこから補助金を交付する」「1台あたりの補助金額が1万円アップの5万5,000円に」「都道府県単位の共通仕様に基づく共同調達を原則とする」の3点だ。
文部科学省は2024年1月に、「学習用コンピュータ最低スペック基準」を公表。その内容は、Windows端末では、OSがWindows 11 ProまたはWindows 11 Education相当になり、CPUがIntel Celeron N4500以上、ストレージが64GB以上、メモリが8GB以上となっている。
Windows 11のシステム要件は、以下の通りとなっている。
Windows 11 のシステム要件
-
プロセッサ:
1ギガヘルツ(GHz)以上で 2 コア以上の
64 ビット互換プロセッサまたは System on a Chip(SoC) - メモリ: 4 ギガバイト(GB)
- ストレージ: 64 GB 以上の記憶装置
- TPM: TPM バージョン 2.0
- グラフィックスカード: DirectX 12 以上(WDDM 2.0 ドライバー)に対応
Windows 10のシステム要件と比較して、Windows 11のシステム要件は、飛躍的に高くなったわけではない。どちらかというと、スペックは、ほぼ据え置きで、トラステッドプラットフォームモジュール (TPM) バージョン 2.0の対応の有無により、古いPCにはインストールできなくなったという認識がある。文部科学省が好評したスペックのほうが、若干、高スペックとなり、現実に即したスペックとなった印象だ。
「GIGA 2.0」対応PCの
起動時間を計測してみた
今回、日本HPのGIGA2.0対応製品「HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC」をお借りすることができたので、実際に起動時間を測定してみた。スペックは以下の通り。
HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PCの
主なスペック
- ペレーティングシステム: Windows 11 Pro Education
-
プロセッサ:
インテル プロセッサー N100
(4コア、6MBキャッシュ、最大3.40 GHz) - メモリ: オンボード 8GB LPDDR5-6400
- ストレージ: 128GB UFS

起動時間の計測は、完全なシャットダウン状態から、Windows 11の待機画面が表示されるまでをストップウオッチで計測した。
10回の起動時間を計ったところ、最短で14.569秒、最長で15.134秒という結果だった。
ちなみにWindows 10搭載のインテル Core i7、メモリ8GB、HDDドライブのPCは、起動に約30秒から40秒ほどかかる。
HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PCのストレージは、UFS(Universal Flash Storage)というフラッシメモリストレージを採用している。この消費電力が比較的少ないUFSの読み込み速度の速さの恩恵を受け、思ったりより起動時間が速いという結果を得られた。
Windowsの起動が遅いという印象としては、HDDからの起動による時間が長かった弊害があるかもしれない。また、ノートPCの場合、電源モードが「最高のパフォーマンス」に設定されていなかったり、「高速スタートアップ」が有効になっていないなど、実力を出し切れていないことも考えられる。
次世代のGIGAスクール構想である「GIGA2.0」対応Windows PCの起動時間は、「思ったよりは遅くない」、というよりは、「飛躍的に速いPC」といえそうだ。
GIGAスクール構想は、GIGA2.0となり、スペック時にもビジネス向けでもPCと変わらない性能となった。ビジネス向けのPCといえば、Windows を搭載したPCがスタンダード。将来、子どもたちが働く環境では、なんらかの形でWindows PCに触れることになる。そんな近い将来のことも考えると、GIGAスクール向けPCもWindows 11 PCが最適であることに間違いない。