|
前回までのお話
服部と赤井は大学の同級生で、日本酒研究会のメンバー。偶然二人きりで飲む機会があり、お互いの悩みを打ち明けあった。
赤井は実家の酒造会社の売上激減に悩み、また服部は大学卒業後個人事業を始めたいのだが、ビジネスプランが見つからず悩んでいた。そんな二人がお互いの問題を解決すべく、日本酒販売を足がかりに個人事業を始める事となった
|
− サーバは、自前?委託? − |
|
「インターネットを使って、実際にどうやって日本酒の販売するか考ないとな。日本酒の注文をとる方法は何か考えているの?」 |

|
「ああ、勿論考えているよ」 |
|
「ショッピングモールに出店するとか?」 |
|
「そうだな、一番簡単なのは大手のショッピングモールに出店する事だね。他には安価なレンタルサーバーやホスティングサービスを使って出店する方法もあるんだけど、毎月の利用料金が結構掛かるし、サーバやOSに制限がある事が多いんだ」 |
|
「そうか。そう言えば、服部は大学の研究室でwebサーバの管理していたよな。服部にはそれだけのスキルがあるんだし、自分達でサーバーを用意してサイトの構築できるんじゃないのか?」 |
|
「自分達でサーバ管理か。まぁ、確かに自宅で管理できると安心なんだよな。バイトである程度の資金は用意している事だし、自分たちでサイトの構築をやってみようか」 |
|
「ああ、僕達二人だけだし、最初からいろいろと制約があったんじゃ意味がないと思うんだ。ほとんど服部まかせになると思うけど、頑張って僕も協力するからさ、僕達でサイトの構築を始めよう」 |
| |
|
| − マシン構成はどうする? − |
|
「自分達のサイトを構築するには、事前にいろいろと準備する事があるよな」 |
|
「ああ、まずは機器を揃えないと。それとサーバの構成をどうするかを決めないとな」 |
|
「ホームページを作るんだから、webサーバが必要なんだよな」 |
|
「そうだ。webサーバだけど、どんなふうに作ろうか。なんかアイデアある?」 |
|
「日本酒の販売だけがメインじゃなくて、写真や解説を取り入れた日本酒に関する情報のページも掲せたいな」 |
|
「そうだね。まずは日本酒のことと、赤井酒造のことをみんなに知ってもらいたいからね」 |
|
「それにできれば、全国各地の日本酒のデータベースを作りたいな。日本酒の情報を貯める貯蔵庫みたいに。将来的にはwebで一般公開できたらいいけど」 |
|
「賛成。そうなるとデータベースの管理もしっかりしないとだめだな。日本酒の販売で顧客情報を取り扱うことになるし、データベースの管理は重要なんだよな」 |
|
「そうそう、顧客情報といえば、今って個人情報保護法だのPマークや、法律とかも整備されつつあるけど、未だに情報漏洩の事件も多いよね」 |
|
「顧客情報のような重要なデータを管理するデータベースサーバはwebサーバとは別個に用意して、インターネット側から直接アクセスできない仕組みにした方が安全だな」 |
|
「わかった。それから僕たちの営業用にクライアントマシンも必要だよな」 |
|
「まずは僕たち二人だけの会社だからクライアントPC2台とサーバー2台を用意しようか。簡単にだけど構成図を作ってみるよ」 |
| |
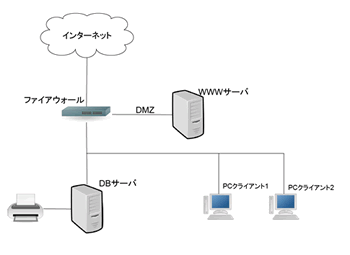
構成図
|
| |
|
| − サーバスペックは?− |
|
「サーバ構成は決まったね、次にサーバーのスペックはどうする?」 |
|
「サイト立ち上げ直後はアクセス数があまりないだろうから、高スペックの必要性はなさそうだからさ、これくらいのスペックにしようかと思うんだ」 |
| |
・プロセッサー: 64ビットインテル(R) Xeon(R) プロセッサー 2.80GHz
・メモリ: 1GB
・ハードディスク: 250GB x 2(RAID1構成) |
|
「ハードディスクは重要なデータを取り扱うし、信頼性が高くないといけないからミラーリング(RAID1構成)にしておこう」 |
|
「ミラーリングって何?鏡でなんか写すのか」 |
|
「あのさ...。ミラーリングっていうのはハードディスクを2台用意して、データを書き込むときに同時に2台に同じデータを書き込むんだ。そうすれば、万が一、1台のハードディスクが故障しても、システムはダウンせずにもう片方のハードディスクでサーバは動き続けることができるんだ」 |
|
「そうなんだ。それからさ質問ばっかりで悪いけど、64ビットって何? なぁ32ビットと64ビットっていったい何が違うんだよ」 |
|
「赤井さ、聞いてばっかりじゃなくて、自分でもちゃんと勉強しろよ。とは言っても、僕もちゃんと説明できないなぁ。そうだ、こんな時こそ先輩に助けてもらおうっと」 |
|
「先輩って?」 |
|
「大学の先輩で、世の中じゃ「謎のエンジニア」と呼ばれている有名人なんだよ。今はとある会社でエンジニアやってるんだけど、何でも知っているし僕の相談役なんだ」 |
| |
|
| − 謎のエンジニア登場!− |
| |
バタンと服部の家のドアが開く音がした。 |
| |
|
|
「よっ!元気にやってるか?」 |
|
「あっ先輩!なんでここにいるんですか?」 |
|
「お前が個人事業を始めるって息まいてたから、様子を見にきたんだよ。あっ君が赤井君だね?服部からいろいろ話は聞いてるよ」 |
|
「はい、はじめまして赤井です。よろしくお願いします」 |

|
「先輩、ちょうどいいところに来てくれた。実は質問があるんです。32ビットと64ビットの違いについて赤井に聞かれてるんだけど、ちゃんと説明できなくて...。説明をお願いできませんか?」 |
|
「唐突なやつだな、わかったよ。32ビットと64ビットの違いはね、扱えるメモリ空間が違うんだよ。32ビット機で扱えるメモリ空間は4ギガバイトが限界で、64ビット機で扱えるメモリ空間は理論上は16エクサバイトなんだ」 |
|
「ギガバイトは聞いた事あるけど、エクサバイトって何ですか?」 |
|
「簡単に言うと、1024ギガバイトが1テラバイトで、その1024倍の1024テラバイトが1ペタバイト、そのまた1024倍の1024ペタバイトが1エクサバイトだから、その16倍が16エクサバイトだよ。」 |
|
「何だか、余計分からなくなったけど、64ビットでは扱えるメモリがとてつもなく大きいということなんですね」 |
|
「そういうこと。よくわかってるじゃないか赤井君」 |
|
「はぁ...」 |
|
「今回、君達が購入するサーバーのメモリは最初は1GBなんだろう。今後拡張する場合、32ビット機ではせいぜいメモリを4倍までしか拡張できないことになるから、64ビット機にしておけば将来のアクセスの増大に対しても柔軟に対応できるぞ。ただし、純粋な64ビット機では現在普及している32ビット版のアプリケーションを動かすことができないから、服部の選択したXeonプロセッサは正解だな」 |
|
「謎の大先生、64ビット機でも種類があるということですか?」 |
|
「いいところに気づいたね、赤井君。実は64ビット機と言っても、純粋に64ビットアーキテクチャで稼動するもの(Intel Itaniumシリーズなど)と32ビットと64ビットアーキテクチャの両方を兼ね備えたもの(俗にEM64Tと呼び、Intel Xeonプロセッサーなど)があるんだ。実を言うと現在では64ビットに移行できていないアプリケーションがまだまだ多いんだ、今の実情を考えるとEM64Tアーキテクチャは最も賢い選択になると思う。蛇足だけど、Intelの互換メーカーではAMD64なんていうアーキテクチャもあるんだ」 |
|
「現在普及している32ビットアプリが使えて、しかも将来の拡張を考慮した64ビット機能を兼ね備えるなんて、宮本武蔵の2刀流みたいで、かっこいいですね。それなら将来アクセス数が増えても安心ですね」 |
|
「そうだよ。それから先々アクセス数や顧客情報、取扱商品とか増えた時のために、メモリやディスクの容量の増設が簡単にできるように、空きの拡張スロットとか空きベイに余裕があるタイプを選んでおくといいよ」 |
|
「ありがとうございました」 |
|
「それと赤井君、僕は「謎の大先生」じゃなくて、「謎のエンジニア」だよ。でもこのままじゃ呼びにくいだろうから、今日からトニーと呼んでくれ。服部もだよ」 |
  |
「はぁ...」 |
|
「じゃ二人とも頑張って。また遊びに来るから。それと分からない事があったらいつでも電話していいからね」 |
|
「えっ、もう帰っちゃうんですか?」 |
| |
|
赤井は呆然と「謎のエンジニア」のトニーを見送った。 |
| |
|
|
「先輩はすごくいい人なんだけど、ちょっと変わってるんだよ」 |
|
「謎のエンジニアって呼ばれている理由がちょっと分かった気がする」 |
| |
|
つづく。。 |
| |
次回予告 −第三話 OSの選択について− |
| |
|
| |
この作品はフィクションです。
登場する人物、地名、団体名等、実在の ものとは、関係ありません。 |
|
|