| |News|にっぽんの元気人|巻頭特集|第2特集|Focus|コラム|イベント|バックナンバー|vol35以前のバックナンバー| |
 |
||
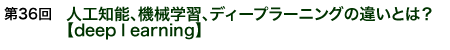 日本のAI技術者が開発した囲碁ソフトが趙治勲名誉名人を破ったことが大きなニュースになるなど、近年人工知能が再び大きな注目を集めている。そのキーワードがディープラーニング(深層学習)と呼ばれる概念である。ディープラーニングは従来の機械学習に較べ、なにが新しいのか? それは人工知能の過去のブームを紐解くことで見えてくる。 |
 |
|
|
||
| 大塚商会の販売最前線からお届けするセールスノウハウマガジン「BPNavigator」のWEB版です。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Copyright 2017 Otsuka Corporation. All Rights Reserved. |
|||||||||||||